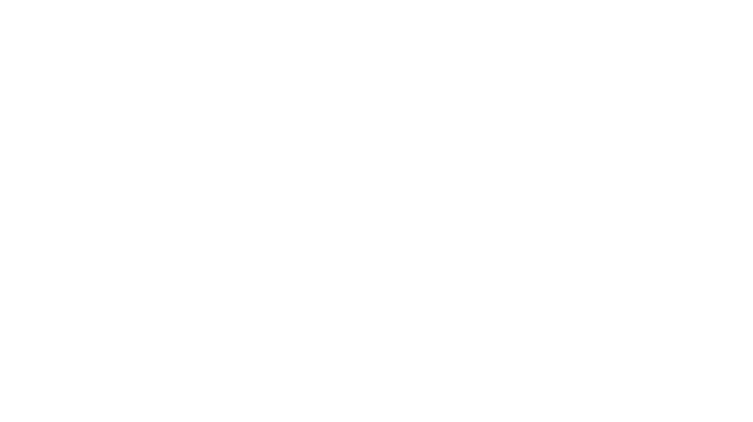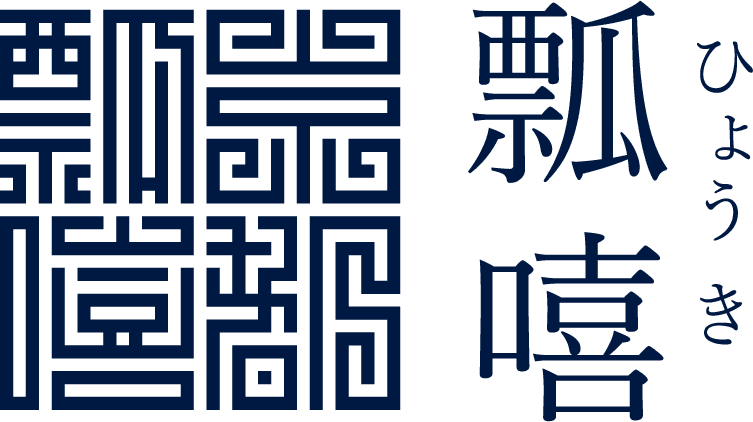すがすがしい初夏のころというと、皆さま、何を思い浮かべられるでしょうか?果物や野菜などの食材はもちろん、天気、草花などいろいろなものがありますが、古くから伝わるお菓子や行事もあります。本日は、陰暦での6月のことを指し、京都発祥である縁起物の和菓子として有名な「水無月」や、茅の輪をくぐり、心身のけがれや、厄を祓い清める初夏の行事として有名な、「夏越の祓(なごしのはらえ)」について、お話させていただきたいと思います。
水無月とは

水無月(みなづき)は、京都市が発祥と言われている、和菓子の一つです。旧暦の6月を意味する「水無月」の名前の通り、6月に食べられる和菓子で、京都では、「夏越の祓」が執り行われる6月30日に、その年の残り半分の無病息災を祈念して食べられています。白いウイロウ生地に、邪気払いの意味をこめた小豆をのせ、暑気を払う氷を表した三角の形をしています。
平安時代、旧暦6月1日の「氷の節句」とされる日に、暑さを乗り切る「暑気払い」として、宮中で食べられていた氷ですが、一般の人々にとっては、貴重でした。そのころに、氷の形を模った三角形の和菓子が作られたのが、始まりだそうです。
三角の形をした白いういろうは、氷を意味すると思に、四角を半分に切ることで、一年の半分を表しているともいわれています。関西ではとても有名な和菓子で、最近では関東でも取り扱割れることが増えてきています。
本来「水無月」は6月を意味しています。現在の日本において6月は梅雨時期のため、「水が無い」という字はピンときませんが、一説には、旧暦の6月は現在の暦に当てはめると、7月下旬から8月上旬のころで、水が少ない時期だったと言われています。また、その他に、「無」という字は現在の「の」の使われ方をされており、田植えの時期で、水が使われる月だったため、「水の月」である、という説もあります。
夏越の祓

日本の伝統的な大祓は、天武天皇の時代には、朝廷が定めた公式行事でもあり、6月の晦日に行われる「夏越の祓」と、大晦日に行われる「年越の祓」の二つがあります。
このうち、「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、古くから6月の晦日(みそか)である、旧暦6月30日に執り行われていた神事です。一年の半分にあたることから、その年半分のけがれや罪を落とし、半年の無事を感謝するとともに、この後の半年における、健康や厄除けを祈願するものです。
起源は、神話として知られる、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の禊祓(みそぎはらひ)と言われており、現在でも、新暦にそのままあてはめ、6月30日ごろに、日本各地の神社で行なわれる行事です。京都の上加茂神社や下鴨神社、大阪の住吉大社で行われている、夏越祓いが有名で、「夏越(なごし)」という言葉は、神様の気持ちを和らげる「和し」という意味があるという説もあります。
厄落としの方法
 夏越祓いは、人形(ひとがた)を用いた厄落としと、茅の輪くぐりという厄落としがあります。
夏越祓いは、人形(ひとがた)を用いた厄落としと、茅の輪くぐりという厄落としがあります。
人形(ひとがた)を用いた厄落としは、息を吐きかけたり、なでたりするなどして、人形に、自らのけがれを移し水に流すことで、厄落としをします。人形とは、人の形に似せた紙の形代(かたしろ)です。人形に代わって、わらなどで作った人形を用いたり、古い毛髪や麻の葉を流すこともあります。また、お清めとして、直接、川や海に入るなどの方法で行う地域もあるようです。
また、「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」も有名です。茅の輪とは、神社の境内に竹で直径2~3メートル程度の輪を作り、チガヤという草で編んだもののことです。参拝する人々が茅の輪をくぐることで、身の穢れや罪を祓うと言われています。茅の輪くぐりは、神社ごとに祭神が異なることから、くぐり方や「神拝詞(となえことば)」が地域、神社により異なると言われています。また、通ることで、人々の罪や穢れをとり祓っているため、茅の輪の草を引き抜いたり持ち帰ったりすることはよくないと言われています。
奈良時代に編集された「備後の国風土記(びんごのくにふどき)」によると、「茅の輪くぐり」もまた、日本神話が由来であるとされています。昔、一人の旅人が現れ、ある兄弟に一夜の宿を乞いました。旅人を冷たく断った裕福な兄、一方、弟の蘇民将来(そみんしょうらい)は、貧しい生活であったが、旅人を迎え入れ温かくもてなしたそうです。数年後、再び訪れた旅人は、スサノオノミコトであり、このとき恩返しとして、授かった腰につける小さなお守りが始まりであるとされています。
もともとは、腰につける小さなお守りだった茅の輪が、次第に大きくなり現在の神事の形となったとされています。暑さを乗り切り、残りの半年を健康に過ごしたいという気持ちは、今も昔も変わらないものですね。
当店では、すき焼き、しゃぶしゃぶをはじめ、様々な旬の食材を使った料理をご用意しております。是非一度当店自慢の料理をお召しあがりになってみてはいかがでしょうか。
皆様のご来店心よりお待ちしております。


 夏越祓いは、人形(ひとがた)を用いた厄落としと、
夏越祓いは、人形(ひとがた)を用いた厄落としと、